第19回:2005年4月9日 KJ法とファシリテーション関西支部
第19回関西地区研究会議事録
■日時 :2005年4月9日(土)13:00〜17:00
■場所 :京都産業会館 2階会議室
■参加者: (確定中)
■担当 :芳本、和己、藤堂
■テーマ:KJ法とファシリテーション
1.今回の狙い
・KJ法とファシリテーションはよく似ている部分がある。
その点を理解していただくと同時にファシリテーションに活用
できるKJ法のテクニックを紹介する。
・上記を実習するプロセスで、実際にFを体験してもらい、
少しでもKJ法をFに活用したときの使い心地を体感していただく。
・個人のスキルアップにつなげる。
・芳本が開発を目指しているKJ法型F(KJ法を活用したファシリ
テーション)の実験台になっていただく。
2.オリエンテーション
・テーマ
『KJ法とファシリテーションは似ている? 』(担当;和己さん)
・内容
まず、川喜田二郎氏の書いた書籍から、ファシリテーションに
関連した著述部分を抜書きし、KJ法型図解を基に、全参加者
にガイダンスとしてご紹介した。
・方法
パワーポイントで作成したスライドを基に、和己さんが説明
所要時間15分
3.実習
その後に、芳本自身が研修業務で使用しているKJ法のテキストの
一部を基に全体を10グループに分けて実習した。
テーマは『上手な読書術』『〜愛知万博に負けるな〜関西万博を
考える』
・方法
ファシリテーター1人+メンバー5人〜6人 ×10チーム
・内容
A型図解+B型文章化 200 分、振り返り 15 分
4.振り返り
各グループから 3 分ずつ実習感想を述べていただいた。
全体的には、KJ法が単純な分類方法だという誤解をしていたなど、
比較的大事なことに気づいていただいたように思う。
しかし、時間がなかったので、 F からフィードバックできません
でしたので、参加者の方に書いていただいたアンケート用紙の
自由意見で振返りの意見の代用をします。
■良かったというコメントをいただいた感想
・導入部分が良かった。 F と KJ 法の関係がよくわかった。
・やはり KJ 法は整理法ではなく、発想法ですね。
・初めて参加したが、非常に良い雰囲気の中で多くのことを学べて
よかった。
・浸透するという概念がわかりにくかった。少し解説があれば
よかった。
・話をする際に発言しやすかった。
・表札作りの研修だけでも面白そう!
・準備が周到に出来ていた。
・KJ法についてポイントをついた研修をしていただきました。
・実際にやってみて習ったことがあった
・ブレーンストーミングがとてもやりやすかった。
・『上手な(読書術)』の定義をはじめに決めておかなくても、
話していくうちになんとなく定まってくるものだというプロセスを
楽しめた。
・最初はイメージできなかったがやってみると面白いと思った。
自分の意見は偏っていると思った。
・合意形成のツールとして活用したい。紐を使った島作りが新鮮で
あった。
・ KJ 法の深さにびっくりした。使いこなすことが出来たらよい
ツールだと思う。
■今後、工夫を重ねるべきという主旨のコメントをいただいた感想
・途中で 1 回、他チームの考え方を簡単に発表させても良かった
のでは?
・自班の F への依存が大きかった。
・今日の感想を最後に言ってもらえたらよかったなと思いましたが、
時間が不足していましたね。
・時間が限られていて KJ 法の細かいところまでは、
今回だけでは理解できない。仕方がないと思う。
 |
 |
| ラベルの関係性を考えながら | 注)この部屋には椅子あり |
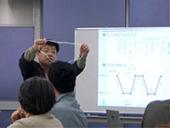 |
|
| ラベルをひもで「島」に |