2022年3月12日(土) テキストからの傾聴と共感~災害エスノグラフィで「勘所」を鍛える~ 関西支部定例会(昼テーマ1)関西支部
開催日
2022年3月12日13:00~17:00
会場
オンライン
ワークタイトル
テキストからの傾聴と共感~災害エスノグラフィで「勘所」を鍛える~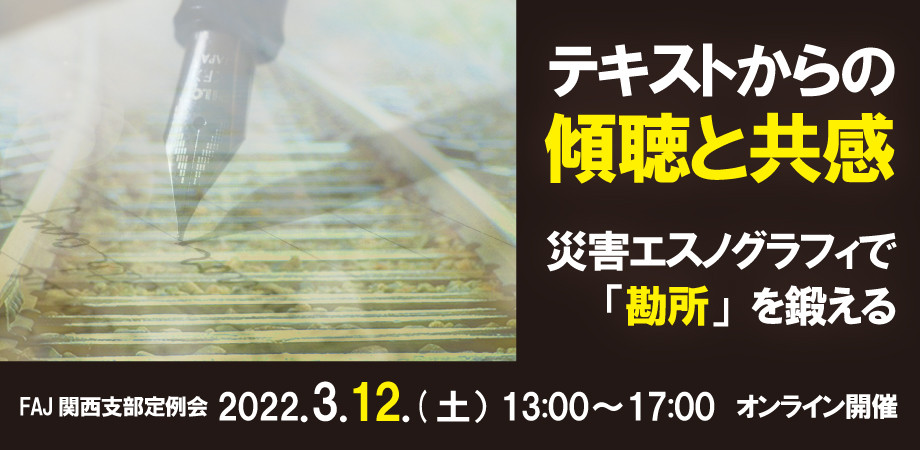
テーマレベル
Pテーマ
MF or チーム代表
企画メンバー
ゆこ、あっきー、ひろ、せら
対象者
誰でもOK テキストから読み取る共感、傾聴のあり方について考えたい方 災害エスノグラフィという手法を通じ、ファシリテーターの勘所(暗黙知)を形式知にして活用したい方 ※災害時の状況の描写(写真・文章など)など心理的に辛くなる場面が出てくる可能性があります。
プログラム概要
13:00~13:20 オリエンテーション(災害エスノグラフィーに関する概説) 13:20~14:30 【ワーク1】読み解き(文章を読み、行動の要因を創造する) 14:30~14:45 休憩 14:45~15:45 【ワーク2】共有・発表(なぜそのような行動をとったかを考え合う) 15:45~16:00 休憩 16:00~16:50 【ワーク3】ふりかえり(ファシリテーターとしての傾聴と共感) 16:50~17:00 クロージング(感想チャットタイム、次回告知など) 17:00~18:00 (任意)ワークふりかえり(残った人で意見交換)
参加者数
ファシリテーター(チーム) [1] 名 +担当運営委員[2] 名+参加者 [20] 名 / 参加者内の会員 [20]名
参加者コメント
- 3つ目のワーク良かったです。傾聴・・・「評価しない。事実をうけとる。」
- 自分の行動・思いを安心して言える場を作ること
- エスノとファシリテーターの最終ゴールは「行動変容」。そのために必要なのは傾聴⇑信頼⇑+共感⇑自己開示
- 公務員=解決策優先、ファシリテーター=行動が変わる、気づく
- 最終ゴールを設定することがファシリテーターのスタート。エスノの最終ゴールは解決策とPDCA
- 「一番大事なところ」という言葉に引きずられて、他の視点が見えなくなった。自分はこのような状況に陥りやすい、ファシリテータの振る舞いとして気を付けたいです。
- 発話者の価値観なぜその発言をしているのかを想像して聞いたとき聞いたことが芯かどうか対話で確認する必要がある
- 話している人ですら気づいていないコト(モノ)に傾聴したり共感したりするためには「時間」との付き合い方が難しいと感じました。
- 私たちは今何の話をしていて、どこへ行きたいのか?を共有することが大事。
- 誰が誰に共感しているのか、誰が何をするべきかの「べき論」を言っているのか、それを声に出していくことが大事。
- 相手が「どうありたいか」を考えながらきくことが大切なのかなと感じました。
- テキストの時間軸が長いので、どの部分の話をしているか、明らかにしていきながら、フォーカスしていけるとよいのかな、と思いました。
- 思いが強い方がいたときは、感情を大事に、そこにフォーカスして大事に思っていることを聞いてみるとよいかな、と感じました。いろんな方がその場にいるから、目的が実はみんな一緒の方向だということを、テーマとして常に意識すると、衝突しないかな、と思いました。
- ファシリテーターとしての傾聴と共感について考えさせる有意義な場でした。
- 災害エスノグラフィの存在も初めて知りましたし、私にとっては、学びのあるカオス体験でした。
- アクティブブックダイアログに似てるなと思ってました。
- 災害が発生したのが、3か月前か5年前かで感じ方も違うかもしれませんね。客観視の度合いが変わってきそう。
- AIがディープラーニングして社員の自由記述欄を読んだら解が導けますかね(笑
- こういう挑戦的な試み大歓迎です。
- いっぱい考える機会になりました。
担当者振り返り
災害エスノグラフィーは、防災対策などを検討するための訓練で用いる技法で、テキストに書かれた言葉から、発話者の意図や感情などを読み取るもの。 定例会としては、災害対応に寄り過ぎないように考え、文字からの傾聴と共感を高めるための手法としてプログラムを試みた。 ワークの大半を黙ったまま読み解き作業に充てるため、オンラインで実施するのは挑戦的だったが、後半のブレイクアウトルームでの対話では、それぞれの共感部分を共有し合うことにより、気づきもあったようす。 今後は、本来の防災訓練のプログラムをブラッシュアップし、HUGに匹敵するようなコンテンツに仕立てていく方向でも検討していきたい。