第1回例会「オープンスペーステクノロジー」in高松四国サロン
4月定例会にご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
四国サロン第1回例会議事録(2009年4月、高松)
■日時:2009年4月25日(土) 12:30〜17:00
■場所:高松市男女共同参画センター 第8会議室
■ファシリテーター:藤井俊行さん(としゆきさん@広島スクエア)
■担当運営委員:武市さん(たけさん)、浮田(議事録)
■参加者:13名(会員7名、非会員6名。香川8名、愛媛3名、広島2名)
■テーマ:「ファシリテーションを使った自由な話し合いに参加しよう!
〜OST(オープン・スペース・テクノロジー)〜」
内容は
◎私たちは、ファシリテーションで、どんな課題を解決したいのか?
◎その課題を解決するために、何を身につけたいのか?
といった、わたしたちの課題を話し合おうという企画。
■ねらい
(1)安全な場(自由な発言が保障された場)での話し合いを通じて、
みなさんがファシリテーションや、四国サロンへ求めるものを考える。
(2)OSTの手法を体験して、そのプロセスを楽しみ、気付きを得る。
全体の進行は、オープン・スペース・テクノロジーの手法に則って進行。
■内容
開始とアジェンダ設定 12:30〜
第一セッション 13:55〜
第二セッション 14:45〜
読み上げ 15:50〜
OSTについて 16:15〜
クロージング 16:30〜16:55
■開始とアジェンダ設定
▽レクチャー (1)「OSTとは?」
1.テーマに関心ある人が集まり、
2.主体的に課題を生み出し、情熱と責任を持って本音の話し合いを行い
3.問題の共有とアクションプランをスピーディに生み出す、全員参加型の
ワークショップである。
[生い立ち]の説明 OSTは1985年に始まり、時代とともに開発。
アプローチやデザイン、開発についてアメリカのコンサルタント
ハリソン・オーエン氏が創始者。
▽本日のテーマ宣言
ファシリテーションでどんな課題を解決したいのか?
どんなことを身につけたいのか?について、話し合いたい議題を挙げてもらう。
[コミュニティ掲示板の作成]
1.思いついた方から、輪の真ん中に出てきて紙とマーカーを一本持って
「議題」を書き、サインをする。
2.それから輪の中で「私の議題は○○で、私の名前は○○です」と発表。
3.そしてその紙をコミュニティー掲示板と案内されている何もない壁に
テープで貼っていく。
4.壁に貼りに行く前に「タイム・スペース・マトリクス(時間割)」に立ち寄り、
時間とスペースを予約する。
5.付箋紙で場所と時間を予約して、コミュニティ掲示板に掲示し、
全員が「議題」を出し切ったと納得いくまで「議題」発表をしていく。
一人何個でも可。
▽レクチャー (1)「OSTの原理と法則」
次へ進む前に4つの原理と1つの法則の説明をする。
○「ここにやって来た人は誰でも適任者である」
○「何が起ころうと、起こるべきことが起こる」
○「それがいつ始まろうと、始まった時が適切な時である」
○「それが終わったときが本当に終わりなのである」
○一つの法則
「主体的移動の法則」
○バンブルビー(はち)とバタフライ(ちょうちょ)
○「えっ?という感覚を大切にしてください。」
創造性を発揮するために「えっ」という感覚を大切にする。
▽マーケットを開く
全員席を立ってコミュニティ掲示板の前へ行き、
好きなだけセッションに申込み、「議題」やアイデアの交換を行なう。
セッションを統合し、キャンセルや変更を、参加者で話し合う。
コミュニケーションをとりながら質問をしてスケジュールを統合する。
■話し合い
・セッションのグループが決まったら、役割を分けて、ホワイトボードや
摸造紙にファシグラしながら進めていく。
・バンブルビー(はち)になって、セッション間を飛びまわっての参加も可能。
・バタフライ(ちょうちょ)になって、自由に好きな場所で羽を休めることも可能。
■発表と投票
各議題について、話し合いの流れを発表し、質疑応答。
その後、参加者全員で、興味深いと思った話し合いに投票
(1番:3ポイント、2番:2ポイント、3番:1ポイント)。
マーケットに出てきた議題(投票数)
・ファシリテーションの学び合う人を増やすためには?(16P)
・本音を引き出す雰囲気の作り方(14P)
・暦を切り口に世の中を見る手法の確立(11P)
・本当の課題をみつけるコツ/目的からずれない話し合いの進め方(11P)
・家族円満のコツ(9P)
・会社の会議を効果的なものにしたい(4P)
・集団の中でうまくしゃべるには?/心の中をきちんと伝わるように
言葉に変えるには?(未カウント)

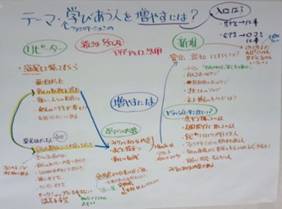
■振り返り:「マインドマップ化」
トーキングスティックを使って、一人ずつ感想・気づきを振り返った。
みんなの言葉をとしゆきさんがマインドマップ化していった。
・いろんな人と話合いができて楽しかった。
・最初の始まりは取っ付きにくかったけど、話し合いが始まると、
あったかくなった。
・グラフィックのやり方にいろんなやり方があって面白かった。
・自分がファシリテーター役をやってみて、うまくできないことが悔しかった。
本気でファシリテーションを学ぶ気になった。
・アイスブレイクがなく始まったので緊張した。
・カタカナ言葉が多く、理解し難かった。日本語化を進めると判りやすく
なると思う。
・何を話すかを自分たちで決めるというやり方は、話し合いを活性化させる
効果があると思う。会社でも使ってみたい。
・決まった議題ではなく、立ち話でずっと語り合う人たちがいた。
どんなことを話しているのか聞いてみたかった。そんな、参加スタイルも
許される自由な場って不思議な感覚だった(いい感じ)。
・Will/Can/Mustの切り口、会社でも使えそう。
・自由な話し合いの場が、四国で開催できてとってもうれしいっ!
としゆきさん、ありがとうございます。
・FAJの名前での参加希望者や、全国のFAJ会員の方からの口コミで
参加してくれた方も多く、「響き合ってる」ことの喜びと感謝、そして、
FAJとしての対応が求められることに身が引き締まった。
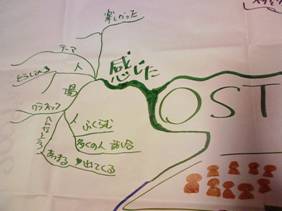 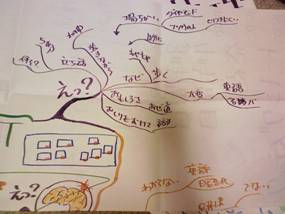 |
|
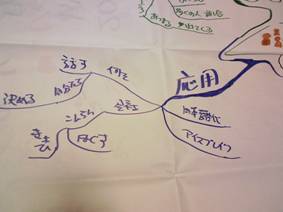 |