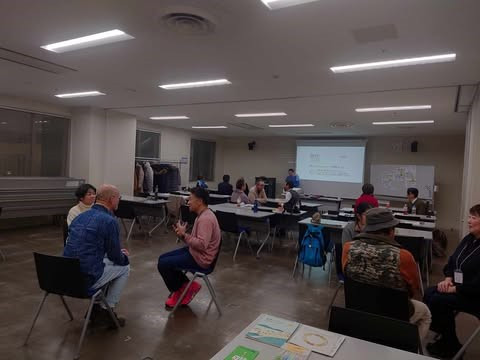2024年12月度 定例会報告:私たちのまちの未来は私たちの話し合いから始めよう 〜北海道での市民ファシリテーターの取組み事例と対話を体験しよう〜北海道支部
テーマ:私たちのまちの未来は私たちの話し合いから始めよう
〜北海道での市民ファシリテーターの取組み事例と対話を体験しよう〜
日 時:2024年12月7日(土) 13:30~16:30 (13:00受付開始)
会 場:札幌市生涯学習総合センター ちえりあ 3F 研修室5・6
参加者:19名 (うち、運営委員6名)
コーディネーター:ばん(板東忍)、すえ(木下紀子)
話題提供者:NPO法人きたのわ 宮本奏さん
■話題提供者からのメッセージ(企画内容)
市民ファシリテーターとは、プロや専門家ではなく、地域に暮らす人たちがまちの話し合いの場にファシリテーションの視点を持って参加したり、小さな話し合いの場をお手伝いできるひとです。 地域の課題解決を誰かにお任せするのではなく、そこに暮らす人たち自身に話し合えた経験があることや、いつでも話し合える場があること自体がまちのチカラとなります。時間はかかりますが、その土壌が育つことこそが、まちの基礎体力となります。 今年3月に『市民ファシリテーターをはじめよう!ガイドブック』を作成しました。実際に取り組んでいる地域が北海道にあるということを紹介させていただき、養成講座のプログラムをみなさんと体験してみたいと思います。
■ワーク概要
「北海道市民ファシリテータープラットフォーム」のはじまり
北海道で育てたい「市民ファシリテーター」って?
対話の練習(聴く・話す・立会うをやってみよう)
■話題提供者からのメッセージ(定例会を終えて)
プロや専門家ではない、地域で暮らす「市民ファシリテーター」の取り組みを始めた地域の事例と、その成果や変化を紹介しました。プロのファシリテーターでは難しいこと、市民ファシリテーターだからできることがあり、市民自治を実現していける可能性に溢れています。後半は、市民ファシリテーター講座プログラムの1つ「対話のワーク」を体験していただきました。
今年団体で作成した【市民ファシリテーターをはじめよう!ガイドブック】をFAJの富山サミットで表彰いただき、今回北海道支部の定例会でお話しする機会をいただき、大変嬉しかったです。
きたのわは、2010年から北海道のまちづくりの現場でファシリテーションの活動を続けてきました。北海道支部のみなさんは2007年から活動を続けてきたと改めてお聞きし、約17年間続けてこられた活動への敬意の気持ちでいっぱいです。いつかどこかでそれぞれが北海道で感じてきたファシリテーションの流れやこれからについて対話してみたいです。ありがとうございました。
■コーディネーターのメッセージ(ばん)
きたのわさんのファシリテーションは丁寧と伺っていましたが、なるほど、と思う対話の時間でした。私は割と沈黙が怖いので、ついつい、余計な相槌をうって、答えを促してしまうところがあるのですが、改めて、待つことの大切さについて考えさせられました。
勝手に、これからのきたのわさんとの長いお付き合いのきっかけができたと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
■コーディネーターのメッセージ(すえ)
以前より、「市民ファシリテーターをはじめよう!ガイドブック」をはじめ、きたのわさんの活動に興味があり、いつかコラボできたら!の念願が叶いました。前半の市民ファシリテーターの活動。促進するというより「ファシリテーション」は育てるという方が近しい気がしました。後半の対話の実戦では、3人ひと組で、話し手、聴き手、立会人となり、それぞれの立場での振る舞い、感覚を体感することができました。参加者の方からも、このような対話の場の必要性を強く感じたとコメントいただきました。また、実践の場でどのようにファシリテーションが使われるのか、その振る舞い、内的プロセスを体感する時間となりました。沈黙は大事なことを探している時間という表現も染み入りました。奏さん、ありがとうございました。
■アンケート抜粋
- 今日の定例会気づきを、どんな行動に移せそうですか?
ファシリテーションを身近に感じてもらうように努めます。
沈黙は大事なことを探している時間と言うのが、心に響きました。
生き甲斐療法になりますね。
学んだこと、気づきを日々のコミュニケーションに活用します
フィードバックのやり方
プロと市民の役割分担が見えてきた
対話の時間設定、6分、3分、1分が勉強になりました。
聴くことに注力してみる。自己開示をしてみる。
まず聴く
- 本日の定例会また今後の定例会に向け、ご意見・ご要望等をご自由にお書きください。
最後のワークは会話の基礎を学んだ気がします。
参加できる限り参加したいと思います。
市民ファシリテーターに興味がわきました。
人と対話することの大切さをまた、体験したいです
いつも居心地の良い場所を提供してくださりありがとうございます