ファシリテーション・サミット富山2024 ワークショップセレクションⅡ
ファシリテーション・サミット富山2023のメインページはこちらをクリック!
ワークショップセレクションⅠ(1日目:6月15日(土)14:45〜16:45)はこちらをクリック!
※ワークショップをまとめた一覧表を準備しました。ワークショップ選択時にご活用ください。
1日目 Fサミット富山2024_WS1_一覧表.pdf
2日目 Fサミット富山2024_WS2_一覧表.pdf
----------
2日目:6月16日(日)10:00〜12:00
2日目のワークショップのテーマとファシリテーターは下表のとおりです。
※詳細は下表のワークショップのテーマ名をクリックしてください。
2日目:6月16日(日)10:00〜12:00
対面開催(富山県民会館)
| No. |
ワークショップのテーマ |
ファシリテーター |
|---|---|---|
| 2-A |
伴場 賢一(ばんば けんいち) |
|
| 2-B | 性的マイノリティとDE&I~トランスジェンダーの診療と社会課題解決の取り組みから~ | 種部 恭子(たねべ きょうこ) |
| 2-C | ビジネスゲームを通じたファシリテーションとウェルビーイングの探求 | 福井 信英(ふくい のぶひで) |
| 2-D | 死生観とウェルビーイング ―喪失をテーマにしたゲーム『運命のダイス』の体験― | 坂井 裕紀(さかい ひろのり) |
| 2-E | 問いの力でSDGsの課題解決を考えよう | 吉田 聖美(よしだ きよみ) |
| 2-F | ウェルビーイング・ダイアログ・カードで、対話をしよう! | 大嶋 友秀(おおしま ともひで) |
| 2-G | 社会的処方×ファシリテーション | 上井 靖(うわい やすし) |
| 2-H | 防災ゲーム「クロスロード」を体験しよう! ~共感・共有の最強コミュニケーションツールを見逃すな~ |
西 修(にし おさむ) |
|
2-I |
NPO活動従事者と、NPO活動におけるWellbeingとその先の受け手に届けるWellbeingを語ろう | 2023年度理事会メンバー コンタクト: 小林政文(こばやし まさふみ)・ 河野 恵(こうの めぐみ) |
2日目:6月16日(日)10:00〜12:00
オンライン開催
| No. |
ワークショップのテーマ |
ファシリテーター |
|---|---|---|
| 2-1 |
issue+design流システム思考 課題の地図を描く技術 powered by Chat GPT |
筧 裕介(かけい ゆうすけ)、 |
| 2-2 |
【開催中止】 |
鈴木 耕平(すずき こうへい) |
| 2-3 (2-I) ハイブリッド |
NPO活動従事者と、NPO活動におけるWellbeingとその先の受け手に届けるWellbeingを語ろう | 2023年度理事会メンバー コンタクト: 小林 政文(こばやし まさふみ)・ 河野 恵(こうの めぐみ) |
<ワークショップ 2-A> 【対面開催】
東日本大震災の経験から~3.11浪江町役場のケースメソッド~
| メインファシリテータープロフィール / 伴場 賢一(ばんば けんいち) アフリカ・東南アジアの貧困削減事業にNPO職員や国連機関・JICA等のコンサルタントとして勤務し、この間住民参加型ファシリテーションを習得。東日本大震災後帰国を機に地元福島に戻りBridge for Fukushimaを設立。復興事業や高校生向けリーダーシップ育成事業に取り組む傍ら復興庁の政策調査官、自治体の総合計画の審議員や政策アドバイザーなども務める。慶應義塾大学 ケースメソッド・インストラクター。 |
 |
ワークショップの概要
東日本大震災において、地震・津波に加え原発の災害を受けた原発周辺20km圏内の自治体では、発災後津波や地震の被害も十分に確認できないまま、避難命令が発令され、短時間のうちに町民・村民の全員の避難を余儀なくされました。その混乱を極める状況の中で避難と避難生活を支えたのは、自分たちも被害者でありながら現場の自治体職員や避難の支援をした団体職員等でした。この貴重な現場での経験を浪江町職員の行動記録とヒアリング結果をケース として、平常時とは異なる緊迫した状況の中様々な意思決定を強いられた職員たちの追体験をケースを通じて経験していただきます。その後自身の優先順位とバイアスそして意思決定過程について分析するとともに、正しい意思決定について議論を行います。
ワークショップの流れ
●アイスブレイク
●ケースリーディング
●意思決定
●グループ内での共有
●全体での共有
●メースメソッド×災害復興のまとめ
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
●想定を超えた震災の発災直後から避難時の追体験
●意思決定プロセスとバイアス
●震災などのKnowlege Transefer(経験共有)のワークショップのデザイン
<ワークショップ 2-B> 【対面開催】
性的マイノリティとDE&I~トランスジェンダーの診療と社会課題解決の取り組みから~
| メインファシリテータープロフィール / 種部 恭子(たねべ きょうこ) 産婦人科医/富山県議会議員。医療で解決できない社会課題に向き合うため2019年統一地方選に出馬。現在、富山県議会議員2期目。 診療に従事しながら医療・福祉政策および女性や子どもの課題に県政で取り組んでいる。 |
 |
ワークショップの概要
トランスジェンダーの診療に携わってきました。仲間を巻き込んで医療体制を作り、葛藤する家族を救い、医療でできる最大限の努力を続けてきました。しかし治療すればするほど、当事者は社会の摩擦で苦しみます。その課題解決のために、医療、福祉、教育、政治など使える手段はすべて使い、当事者も巻き込んで取り組んできました。しかし性的マイノリティに対する攻撃は激しく、多様性の受容への道のりは長いと感じています。Diversity, Equity & Inclusionの過程での変化と課題解決が社会の利益につながることは確かですが、人は変化への不安から防御的になる生き物です。どうやって安心材料を社会にちりばめるのか、皆さんとともに考えたいと思います。
ワークショップの流れ
トランスジェンダーとその医療および社会課題への取り組み(トーク)
性的マイノリティとDiversity, Equity & Inclusion (課題解決に向けてワーク)
性的マイノリティ(LGBTQ)を学校や企業等組織で受け入れる取り組みを考えている方
<ワークショップ 2-C> 【対面開催】
ビジネスゲームを通じたファシリテーションとウェルビーイングの探求
| メインファシリテータープロフィール / 福井 信英(ふくい のぶひで) 株式会社プロジェクトデザイン代表 |
 |
ワークショップ概要
株式会社プロジェクトデザインは、2010年に富山で創業して以来、200を超えるビジネスゲームを通じて組織と個人の変革を支援してきました。 私たちのゲームは現実の社会で起こる出来事を再現し、体験と振り返りを通じて参加者が「個々の行動が組織や社会にどのような影響を与えるか」「現実を生み出しているのは私たちの価値観や行動であること」を実感する機会となっています。
このワークショップでは「社会や組織の問題にわたしたちがどのように取り組むか」というテーマを含むビジネスゲームを体験します。 そして、振り返りを通じて、個人としても組織としても成長のきっかけを掴み、ウェルビーイングが高まるプロセスをふり返ります。 ふり返りを通じて、ファシリテーションの更なる可能性を引き出すことに寄与できれば幸いです。
ワークショップの流れ
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
<ワークショップ 2-D> 【対面開催】
死生観とウェルビーイング ―喪失をテーマにしたゲーム『運命のダイス』の体験―
| メインファシリテータープロフィール / 坂井 裕紀(さかい ひろのり) 1974年富山県出身 東京大学大学院情報学環 特任研究員(2023年より現職) 早稲田大学大学院人間科学研究科修了(博士(人間科学)) 専門は教育工学,臨床死生学,ゲーミフィケーション。 これまでに心の健康の保持増進に関するワークショップや研修を1000回以上行っている。 |
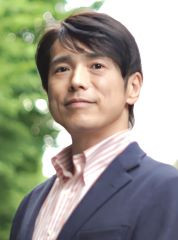 |
ワークショップの概要
近年,ゲームのポジティブな要素を健康・教育・仕事などに役立てようとする取り組みが「Gamification」と呼ばれ,実践報告が増えている。また,Vuorre et al.(2022)の研究では,ゲームをプレイする動機がWell-beingに正の影響を及ぼすことを報告している。そして,Tal Ben-Shahar(2021)は,Well-being向上のために「SPIRE」の重要性を提唱している。本ワークショップではSPIREとGamificationを参考にデザインされた3つのワークを体験できる。本ワークショップが,参加者とその家族のWell-being向上の一助となれば幸いである。
ワークショップの流れ
1.イントロダクション
2.アイスブレイク/チェックイン
3.レクチャー:死生観とWell-being
4.ワーク①:私の大切な物事カードの作成
5.ワーク②:私の大切な物事カードの紹介
6.ワーク③:ゲーム『運命のダイス』の体験
7.リフレクション:体験の省察
8.シェアリング:印象や学びの共有
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
・ゲームを用いたワークショップに興味のある方
・SPIRE(特にEmotional(情動性))に関心のある方
・人生の大切な出来事を考えたい方
・喪失体験からの成長に興味のある方
・死生観とWell-beingに関心のある方。
<ワークショップ 2-E> 【対面開催】
問いの力でSDGsの課題解決を考えよう
| メインファシリテータープロフィール / 吉田 聖美(よしだ きよみ) 団体名「ファシリテーションをはじめよう」佐竹正人、増平貴之、吉田聖美 2017年、会議や話し合いの困りごとをファシリテーションで解決してもらいたい!との気持ちからファシリテーションを広めることを目的に活動開始。 70回以上のワークショップを企画し、400名以上が参加。 この1年もFAJ定例会の企画や支部イベントでのワークショップ実施、東京都主催イベントでのワークショップ実施など、FAJ内外で活動。 |
 |
ワークショップの概要
ファシリテーションのスキルの1つに「問い・質問」があります。
その「問い」に着目したワークショップを、この10年で100社以上の企業を質問で元気にしてきた河田真誠さんが開発した「問活ノート」を使って体験します。
2024年2月の東京支部イベントでは、この問活ワークショップをウェルビーイングと結び付けて行い、参加者の方からは以下のような感想をいただきました。
・質問にたくさん答えて、久々に頭フル回転でした。
・対話の時間が多くて良かったです。考えを深められました。
・普段考えないお題で考え、自分を振り返ることが出来ました。
・ただ問いに集中して考えられました。
今回、問活ノートの問いを使って考えるのは、基調講演を担当される南雲氏も造詣が深いSDGsの17の開発目標のうちの1つ。
質問に答えることで自分の中の答えを知り、対話を通じて課題解決のヒントを得る機会を提供します。
ワークショップの流れ
・複数の問いを段階的に投げ、個人で考える、グループでシェアする、という流れを繰り返します。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
<ワークショップ 2-F> 【対面開催】
ウェルビーイング・ダイアログ・カードで、対話をしよう!
| メインファシリテータープロフィール / 大嶋 友秀(おおしま ともひで) メインF:大嶋友秀ー東京支部、コF:久保田和宏ー東北支部が、ウェルビーイング・ダイアログ・カード認定ファシリテーター)また、大嶋友秀は、ウェルビーイング学会、ウェルビーイングとコミュニケーション研究部会メンバー。他に、国際ファシリテーターズ協会(メンバー)、IFVP(International Forum of Visual Practitiors、 メンバー)、ワールド・カフェ・コミュニティ・ファウンデーション(国際理事)、生成的会話の場コミュニティ(GCBC)の理事長。 |
 |
ワークショップ概要
今、ウェルビーイング(幸福学)は、これからの組織活動を考える上で欠かせないものです。そもそも、なぜ働くのかと問えば、幸せになるためではないでしょう。しかし、それは簡単ではありません。個人の幸せも、組織の幸せも、その必要性に気づき、自分やまわりのひとたちの意識や認識が変わらないと、ウェルビーイングになる行動にもつながりません。
そこで、ウェルビーイング・ダイアログ・カードに注目したいのです。
これは、幸福学の先駆者である、慶應義塾大学の前野隆司先生と、前野マドカ先生が開発されたものです。トランプに準えた52枚のカードに質問が書かれています。このカードは、幸せの4つの因子に沿って、数字の若い番号から、質問の難易度が上がるようになっています。その一枚一枚の質問は、全てこれまでの研究成果や実験データに裏打ちされています。
カードの質問は、人生の中でウェルビーイングになるための大切なことについて聞いてくれます。そのため、このカードを使ってダイアログをすることが、ウェルビーイングへの認識を高め、その人も組織にも良い影響が出てくるというのです。そして、その効果を活かすためには、ファシリテーションが必要になります。
今回のテーマ「ウェルビーイング社会~課題を解決するファシリテーション」を考えるとき、ウェルビーイング・ダイアログ・カードを使い、気づきや学びを誘発するダイアログをもてるようにファシリテーションすることが大切です。
このワークショップでは、ウェルビーイング・ダイアログ・カードの説明をします。そして、カードを使ったダイアログセッションをグループワークで行います。その中で、ファシリテーションの重要性も感じてもらいます。
また、このカードは、いろんなワークショップに使える応用性が高いこともあります。このカードを活用した、造形ワークショップなど事例も紹介する予定です。
ワークショップの流れ
・ウェルビーイング・ダイアログ・カードの説明
・ウェルビーイング・ダイアログ・カードを使った対話の実践(グループワーク)
・気づき(グループ→全体)
・ウェルビーイング・ダイアログ・カードの応用事例の紹介
・Q&A(及びふりかえり)
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
<ワークショップ 2-G> 【対面開催】社会的処方×ファシリテーション
| メインファシリテータープロフィール / 上井 靖(うわい やすし) A-sessions 代表、愛知みずほ大学特任教授、NPOアスクネット理事 名古屋市のキャリア教育・学習支援・フリースクールに関わっている。 コミュニティーコーピング認定ファシリテーター 元名古屋公立中学校長、FAJフェロー |
 |
ワークショップ概要
英国では、患者の健康やwell-beingの向上などを目的に、医学的処方に加えて、患者を地域の活動やサービス等につなげる社会的処方(social prescribing)と呼ばれる取り組みが進んでいます。例えば、メンタルヘルス不調の患者に、薬の処方箋に頼るのではなく、地域の交流会やウォーキングサークルの活動に参加することによって、孤独感が緩和され、心と体と社会的に良い状態になることが期待されます。さらに、通院の回数や医療費が減ることにもつながります。この取り組みには、リンクワーカーという役割を担う方が必要となります。地域住民同士の顔が見える関係づくり、町づくり、医療、福祉、文化等の個人・団体とのネットワークづくりなど地域を包括し、人と人・コミュニティ・機関をつなぎ、人や地域のwell-beingに発展する役割を果たします。このリンクワーカーをはじめとする役割に、ファシリテーションは不可欠という仮説を持ちました。
このサミットセレクションでは、社会的処方とは何か?ファシリテーションはどんな役割、場面に対して活用できるか?などについて探るワークショップを開きます。内容として、①ミニレクチャー「社会的処方とは?」 ②社会的孤立を解消する協力型のゲーム*「コミュニテーコーピング」を体験&振り返り ③地域での実践(ファシリテーションを活用)例紹介 ④社会的処方でのファシリテーションの可能性を探るワークショップ です。今回のサミットのテーマに迫るワークショップをみなさんと一緒に創りあげましょう!
*「コミュニティコーピング」は、(一社)コレカラ・サポートが開発した人と地域資源をつなげることで「社会的孤立」を解消する協力方ゲームです。
ワークショップの流れ
①ミニレクチャー「社会的処方とは?」
②社会的孤立を解消する協力型のゲーム「コミュニテーコーピング」を体験&振り返り
③地域での実践(ファシリテーションを活用)例紹介
④社会的処方でのファシリテーションの可能性を探るワークショップ
◯このワークショップの協力者(コミュニティーコーピング認定ファシリテーター、F A J会員)として、横山祐一(よこやまゆういち)さんと共に進めていきます。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
地域や社会課題に対して、ファシリテーションを活用したいと思われている方
〇定員 12名程度
<ワークショップ 2-H> 【対面開催】
防災ゲーム「クロスロード」を体験しよう! ~共感・共有の最強コミュニケーションツールを見逃すな~
| メインファシリテータープロフィール / 西 修(にし おさむ) 再開発事業をスタートに様々なまちづくりに携わる中でワークショップに出会い、2002年「神戸まちづくりワークショップ研究会」を結成。事例研究やプログラム開発、運営支援を行っている。 2005年9月「神戸クロスロード研究会」設立に参加、阪神・淡路大震災での自らの被災体験に加えて、ワークショップのノウハウを活用したプログラム開発を行うなど、阪神淡路大震災の体験を伝えるクロスロードの普及活動に取り組んでいる。 |
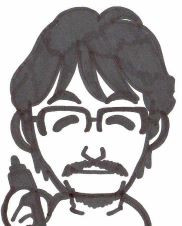 |
ワークショップ概要
「あなたは避難所の食料担当。被災から数時間。避難所には3,000人が避難しているとの確かな情報が得られた。現時点で確保された食料は2,000食。以降の見通しは今のところなし。まず、この2,000食を配る?」
あなたはの答えはYes?それともNo?
元旦の能登半島地震に明けた2024年、現場は多くの悩ましい選択に迫られたことでしょう。
クロスロードは、阪神・淡路大震災で実際に起きたできごとや教訓をもとに作られたカードゲーム形式の防災教育教材です。
クロスロードとは「岐路・分かれ道」を意味する言葉。私たちは日々の様々な場面においてクロスロードに立ち、選択しています。あなたはそのジレンマにどう向き合っていますか?その選択に自信はありますか?
ジレンマあるところクロスロードあり。クロスロードは、今では環境・子育て・ケースワーク・ダイバーシティなど多岐にわたったテーマで取り上げられ、コミュニケーションツールとしての活用の世界を広げています。
クロスロードはシンプルなルールのゲームの中に細やかな仕掛けが練りこまれたファシリテーションツールでもあります。普通なら取り扱いにリスクを伴う話題も、ゲームという形式をとることによって、そのハードルを軽々と飛び越え、深い対話を作り出す力を秘めたツールです。
FAJが初めて全国イベントとして開催したFF2007で紹介して以来、17年ぶりに全国イベントでの登場です。初めての方は是非この機会に体験してください。
ワークショップの流れ
防災ゲーム「クロスロード」を体験します。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
<ワークショップ 2-I> 【対面開催、ハイブリッド開催】
NPO活動従事者と、NPO活動におけるWellbeingとその先の受け手に届けるWellbeingを語ろう
| メインファシリテータープロフィール / 2023年度理事会メンバー コンタクト: 小林 政文(こばやし まさふみ)・河野 恵(こうの めぐみ) 2023年度理事会のメンバー |
 |
ワークショップ概要
私たちは、なぜNPO活動に従事しているのか? NPO活動が、社会課題解決に寄り添うためにどんなWellbeing Mindがあるのか? また、私たちFAJ会員の活動や他NPO団体の活動とともにWellbeingに寄与できるもの、また自身のWellbeingも含めた視点で、フラットな立場で深い対話をしてみませんか?
ワークショップの流れ
深い対話の場をつくり、今までの各活動の取り組みを含め、自分自身のWellbeingがどの様に影響を与え合っているのか?また、NPO活動におけるWellbeingを話す時間を共有する。 短い時間ですが、深い対話の場を作って、心に残る、この先ずっと自分に問いかける"問い"を生み出したい。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
<ワークショップ 2-1> 【オンライン開催】
issue+design流システム思考 課題の地図を描く技術 powered by Chat GPT
*本プログラムは、スタートが30分早い9時30分から(12時まで)となります。
|
メインファシリテータープロフィール / メインファシリテータープロフィール / |
 |
メインファシリテータープロフィール / 筧 裕介(かけい ゆうすけ)
issue+design代表。「SDGs de 地方創生」「SDGs de未来構想」他、デザイン思考を活用した各種ワークショップを開発。
メインファシリテータープロフィール / 澤田 直子(さわだ なおこ)
i+dコミュニティデザイナー。 千葉県手賀沼エリアのまちづくりや小学校相談業務などに従事電気通信大学通信工学科卒業、㈱東芝でシステムエンジニアとして働いたのちキャリアチェンジ。オンラインオフライン共にコーチングやNLPをベースにしたコミュニケーションワークショップの企画、運営、講師を務める。メタバースVR内でもファシリテーション講座や対話の場を作っている。
ワークショップの概要
名著「学習する組織」他、様々な有識者や書籍で重要性が指摘されている「システム思考」。
この思考法の重要性はよくわかるものの、仕事や地域づくりなどの現場で活用することが難しいと感じてる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。issue+designでは、「持続可能な地域のつくり方(筧裕介著)」他で活用したイシューマップ(課題の地図)を描くことで、システム思考を誰もが習得できるワークショップを開発しました。また、システム思考には、包括的・俯瞰的な視点の拡張が欠かせません。そのために独自開発したChatGPTによるサポートシステムを活用したワークショップを体験いただきます。
ワークショップの流れ
講義 システムとシステム思考とは
演習1 あなたの課題を探求する
演習2 AIとともに視点を拡張・深化する
演習3 課題の地図を描く
講義 システム思考のプロセス
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
次のような問題意識を持つビジネス・行政・まちづくり、ソーシャルセクターの方
1. システム思考を学習・習得したい
2. より俯瞰的・包括的視点で課題を捉えたい
3. 複雑で入り組んだ課題を見える化・可視化・構造化したい
<ワークショップ 2-2> 【オンライン開催】
【開催中止】
理由:メインファシリテーターの鈴木耕平様が所要により登壇できなくなりました。
富山での3つの事例(集落、循環型農業、研究者/行政/住民の対話)をヒントに実践を考える、オンラインツールmiroを活用した参加型ワークセッション
| メインファシリテータープロフィール / 鈴木 耕平(すずき こうへい) 株式会社たがやす代表取締役。 北海道大学大学院環境科学院修了、食品メーカー技術職を経て現職。 富山に移住し「一人ひとりが輝く土壌をつくる」を軸に、企業 / 行政 / 研究機関での対話と見える化の技術を生かし、現場での対話から参加者の内発的な動機が生まれる場づくり、必要な意見の抽出と合意形成を図っている。 |
 |
ワークショップの概要
「ウェルビーイング社会へ、課題を解決するファシリテーション」というテーマに即して考えると、富山県には活かせる資源と課題がたくさんあります。答えがない中で、具体的な課題を話し合い社会実装する際には、一部の知見に基づいて意思決定を行うと、トレードオフとして不利益を被るステークホルダーが生じる可能性もあります。
皆さんの日常で周りを見渡してみると、どのような課題が見えてくるでしょうか?
今回は3つの事例を紹介し、皆さんの身近にある課題やできることを共有し、ファシリテーションの先にある地域や社会の可能性を探りたいと思います。
対話と知見の共有から、一人ひとりの実践につながるヒントを探求しましょう。
ワークショップの流れ
・オープニング(導入とチェックイン)
・ウェルビーイングを目指す3つの事例共有 *40軒〜400軒ほどの集落での地域運営組織づくり *給食を起点に生産者と消費者を繋ぐ循環型農業への挑戦 *科学者と行政と住民で流域から考える地域の暮らし
・対話の時間
・クロージング(振り返りとチェックアウト)
※オンラインホワイトボードツールを使用するため、PCでの参加を推奨します。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)
・場として:職場・教育現場・家庭での実践
・機会として:人の実践事例を聞く、アイデアを交流し自分の実践に持ち帰る、自分のできることに気づく、やりたいことのヒントを得る
・役割として:人を巻き込みたい、頑張っている人のサポートをしたい、自分のコミュニティで企画したい
・スキルとして:オンラインホワイトボードmiroの活用・zoomでのコミュニケーション、グラフィックファシリテーション
<ワークショップ 2-3> 【オンライン開催、ハイブリッド開催】
NPO活動従事者と、NPO活動におけるWellbeingとその先の受け手に届けるWellbeingを語ろう
メインファシリテータープロフィール / 2023年度理事会メンバー コンタクト:小林 政文(こばやし まさふみ)・河野 恵(こうの めぐみ)
2023年度理事会のメンバー
ワークショップの概要
私たちは、なぜNPO活動に従事しているのか? NPO活動が、社会課題解決に寄り添うためにどんなWellbeing Mindがあるのか? また、私たちFAJ会員の活動や他NPO団体の活動とともにWellbeingに寄与できるもの、また自身のWellbeingも含めた視点で、フラットな立場で深い対話をしてみませんか?
ワークショップの流れ
深い対話の場をつくり、今までの各活動の取り組みを含め、自分自身のWellbeingがどの様に影響を与え合っているのか?また、NPO活動におけるWellbeingを話す時間を共有する。 短い時間ですが、深い対話の場を作って、心に残る、この先ずっと自分に問いかける"問い"を生み出したい。
役に立つ場面(こんな方にお勧め)